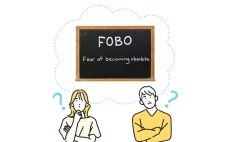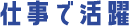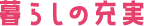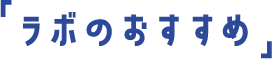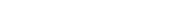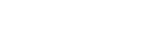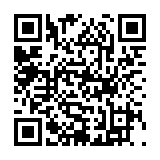転職1年目、なんでも相談室
「人前で話すのが苦手…」から一歩前進。スピーチの専門家が教える職場で使える3つのメソッド
会議内での発表や朝礼でのスピーチ。特に新しい職場では「変に思われたらどうしよう」「評価が下がるかもしれない」という不安から、人前で話すことへの苦手意識がさらに強まってしまうものです。聞き手が「ミスを指摘しようと意地悪い目線で見ているかも」や「関心が無くて聞いていないかもしれない」と想像するだけで緊張してしまい、頭が真っ白になりそうになることはありませんか?
公開 : 2025/10/28 更新 : ----/--/--
新しい職場・仕事で活躍するには何が必要?
転職1年目、なんでも相談室
本連載では、転職後のさまざまな壁を乗り越えて、新しい職場で活躍するためのコツをアドバイス! 入社直前の不安な気持ちから、入社後の仕事・人間関係のトラブルまで、転職後1年目に起こりうる「あらゆるお悩み」を取り上げていきます。
みんなの前で話すのがとにかく苦手。どうすれば克服できますか……
転職してもうすぐ1年。日々の業務には慣れてきましたが、どうしても慣れないのが人前での発言です。数人のチームミーティングならまだしも、部署全体が集まる会議での発言や、ましてやプレゼンとなると、落ち着こうと思っても緊張してしまいます。声は震え、手には汗。準備してきた内容も、視線を浴びた瞬間に飛んでしまい、しどろもどろに…。周りの同僚が堂々と話しているのを見ると、自分だけができていないように感じて落ち込みます。
「人前で話す力」は、身につけられる “ビジネススキル” です

こんにちは、『転職そのあとLABO』です。
今回のお悩みは、「人前で話すのが苦手で、どうしても緊張してしまう」というものですね。以前のアドリブ力のお悩みにも通じるところがありますが、こちらは「準備していても、うまく話せない」という、さらに切実な悩みかと思います。
私も人前で話すのがとても苦手でした。お客さんへのプレゼンだけではなく、朝礼で話すような短くて柔らかい内容のショートスピーチも下手で、後から反省…なんてことも度々経験しました。
ですが、「話す力」はセンスではなく、トレーニングで身につけられるスキルだと知りました。今回は、スピーチの専門家たちのメソッドも参考にしながら、私が実践して特に効果があった「人前で話す力」を鍛えられる3つの方法をご紹介します。
1、「緊張」の解像度を上げて味方につける
まず、一番最初に取り組むべきは、敵だと思っている「緊張」について理解することです。人前で話すのが苦手な人は、「いかに緊張しないか」ばかりを考えてしまいがちですが、実はそれが逆効果だと言われています。
緊張するのはネガティブではない
そもそも、なぜ人前で話すときに緊張するのでしょうか。それは、「うまくやりたい」「良い評価を得たい」「失敗したくない」という気持ちがあるからです。つまり、緊張とは、あなたがその場に真剣に向き合っている証拠に他なりません。どうでもいいと思っていることで、人は緊張しないのです。
心拍数が上がって、少し暑くなるような感覚に…。こうした身体的な反応は、あなたの脳が「これは重要な場面だ!」と認識して、パフォーマンスを発揮するためにアドレナリンを分泌している状態。いわゆる交感神経が優位になって、身体が「戦闘モード」に入っているサインです。
そう考えると、緊張は決してネガティブなものではないと思えませんか?「緊張してきたな。よし、集中力が高まってきた証拠だ」と、その感覚を受け入れてみてください。「緊張してはいけない」と抑え込もうとするから苦しくなるのです。「緊張してもいい。むしろ、最高のパフォーマンスのために必要なものだ」と捉え方を変えるだけで、少し気持ちは軽くなります。これはスポーツ選手もよく言っていることだと思います。
緊張をエネルギーに変える具体的なアクション
とはいえ、過度な緊張はパフォーマンスを下げてしまいます。そこで、緊張を「適度な集中力」に変えるための簡単なアクションをご紹介します。
スピーチの直前に、ゆっくりと深い腹式呼吸を3回行う。(息を吸う時間より、吐く時間を2倍長くするのがポイント。副交感神経が優位になり、心拍数が落ち着きます)
「今日は少し緊張しています」と最初に言ってしまう。 (カミングアウトすることで気持ちが楽になりますし、聞き手も「頑張れ」と温かい目で見てくれることがあります)
物理的に体を動かす。(発表前に少し歩いたり、肩を回したり、手のひらをグーパーするだけでも、筋肉の硬直がほぐれ、リラックスできます)
緊張をなくそうとするのではなく、「制御可能なエネルギー」として手なずける。これが、人前で話すための最初のステップです。
2、スピーチは「対話」、司会進行の視点を取り入れてみる
次に、スピーチに対する考え方を変えてみましょう。多くの方が、スピーチを「自分一人が、大勢に向かって伝えるべきこと話すこと」と捉えています。この「一対多」の構図がプレッシャーに繋がります。
そこでおすすめしたいのが、「自分はスピーカーではなく、この場の“司会進行役”だ」という視点を持つことです。
なぜ「司会者」の視点なのか?
テレビ番組や動画コンテンツの司会者を思い浮かべてみてください。彼らは堂々としていて、スムーズに場を回していきますよね。司会者とスピーカーには、多くの共通点があります。
ゴールが明確: その場(番組・スピーチ)をどこに導きたいかがハッキリしている。
時間管理: 決められた時間内に、伝えるべきことを伝える意識がある。
聞き手への配慮: 観客やゲスト(聞き手)が理解しやすいように、言葉を選び、場の空気を作る。
スピーチのうまい方は、無意識にこの「司会者」の役割を果たしています。彼らは一方的に話しているのではなく、聞き手の反応を見ながら、意識のキャッチボールをし、その場全体を適切なペースでゴールに向かって進行させているのです。
こう考えるとスピーチの内容も構成も変わってきます。「うまく話したい、考えを伝えたい」という自分本位の視点から、「どうすれば、最も効果的に伝わるだろうか?関心を持ってもらえるだろうか?」という他者本位の視点に切り替わるのです。
実際に「司会者」としてスピーチを考え直してみましょう
聞き手を「お客様」としてもてなす意識を持つ。 「貴重なお時間をいただいているので、〇〇について端的にお伝えします」「普段はあんまりご関心ないかもしれませんが〜」というように、聞き手への気遣いと感謝をするだけで、独りよがりなスピーチではなくなります。
聞き手の反応を“サイン”として受け取る。聞き手が頷いていれば、「伝わっているな」と自信を持つ。少し難しい顔をしていたら、「この部分は、もう少し丁寧に説明しよう」と軌道修正する。オフラインでもオンラインでも聞き手の反応は重要です。
問いかけを適度に使う。 「皆様は、〇〇についてどう思われますか?」と実際に問いかけなくても、「ここで一つ、想像してみてください」といったフレーズを入れるだけで、聞き手は自分事として話を聞くようになり、場に一体感が生まれます。
話す内容を丸暗記しない。聞き手の反応を見ながら柔軟に話すわけですから、原稿をそのまま読むわけにはいきません。丸暗記はしないで、流れとポイント(次項で説明)は押さえて臨む方が良いでしょう。
「自分が主役」ではなく「自分は進行役」。この意識の転換が、「見られている」というプレッシャーを、「場をリードしている」という自信へと変えてくれるはずです。トレーニングとして実際の会議の進行をやってみるのも良いかもしれません。
3、“王道のメソッド”で、伝わる構造と表現を身につける
最後に、より実践的な技術について触れます。自信を持って話すには準備が必要です。「伝わる構造と表現」を意識して話す内容を考えましょう。ここでは、多くのスピーチ専門家が推奨する、普遍的なメソッドをご紹介します。
伝わる構造を作る「PREP(プレップ)法」
ビジネスシーンにおける報告・説明の基本として有名な「PREP法」は、スピーチにおいても効果があります。
P = Point(結論): 「私が本日お伝えしたい結論は、〇〇です」
R = Reason(理由): 「なぜなら、〇〇という理由があるからです」
E = Example(具体例): 「具体的には、〇〇というデータや事例があります」
P = Point(結論): 「以上の理由から、私は〇〇が重要だと考えます」
なぜこの構造が強いのか? それは、聞き手が最も知りたい「結論」から話すことで、聞き手の頭の中に「話の地図」が最初に描かれるからです。この地図があるおかげで、聞き手は話の途中で迷子になることなく、安心してあなたの話についてくることができます。スピーチの原稿を作るときは、まずこの4つの要素を書き出すことから始めてみてください。
より「伝わる表現」にブラッシュアップする
これまでのことがある程度できるようになったら、伝え方を磨いてみましょう。話す内容と同じぐらい、どう届けるかは重要です。棒読みではせっかくの内容も響きません。こちらも定番のメソッド3点を意識してみてください。
1.「間」を使って抑揚をつける。つい沈黙が怖くてつい早口で切れ目なく話しがちですが、「間」をうまく使うと聞き手の注意を引きつけることができます。伝えたいキーワードの直前で、意識的に「1秒」の間を取ってみましょう。それだけで、印象的に伝えることができます。
2.視線は「Z」を描くように。聞き手の人達を前にして、どこを見ていいか分からず、あらぬ方向や手元の資料に視線が落ちていませんか? 体の向きを変えながら、アルファベットの「Z」を描くように、ゆっくりと目線を配ってみましょう。特定の誰かと目を合わせるのが難しければ、相手の眉間あたりを見るだけでも構いません。
3.ジェスチャーは「少し大げさ」がちょうどいい。場のフォーマル度合いにもよりますが、いつもより少し大きい身振り手振りを交えてみましょう。躍動感が生まれますし、話す側もリラックスできます。数字を示すときに指を使ったり、範囲の広さを示すときに両手を広げたり。ちょっとオーバーかなと感じるくらいが、自信があるように映ります。
まとめ

いかがでしたでしょうか。今回紹介した3つのメソッド――①緊張をネガティブに捉えず味方につける、②「司会者」の視点で場を進行する、③「PREP法」や「間」などの王道テクニックで準備する――を意識すれば、人前で話すのが苦手な方でも少しずつ苦手意識は克服されて、自信を持って話せるようになります。