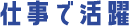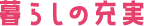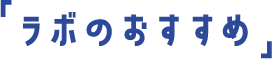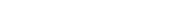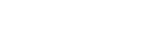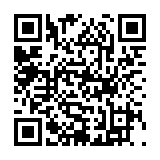転職1年目、なんでも相談室
AIに仕事が奪われる? 「時代遅れになる恐怖(FOBO)」と、私たちのサバイバル術
AIが仕事を劇的に効率化してくれる。その恩恵を受ける一方で、心のどこかで「自分のスキル、このままで大丈夫?」と、ふとした瞬間に不安がよぎることはありませんか。実はその正体は「時代遅れになる恐怖(FOBO)」かもしれません。この記事では、そんなモヤモヤした不安と向き合うための、ある企業のオンライン社内勉強会「オシゴトカイワイ」の様子をお届けします。AIと共存する未来を前向きに生き抜くためのヒントを、彼らの対話から見つけにいきましょう。
公開 : 2025/09/30 更新 : ----/--/--
新しい職場・仕事で活躍するには何が必要?
転職1年目、なんでも相談室
本連載では、転職後のさまざまな壁を乗り越えて、新しい職場で活躍するためのコツをアドバイス! 入社直前の不安な気持ちから、入社後の仕事・人間関係のトラブルまで、転職後1年目に起こりうる「あらゆるお悩み」を取り上げていきます。
【オンライン社内勉強会 オシゴトカイワイ】
<登場人物>
はたけ: 社内オンライン勉強会のファシリテーター。データ分析や海外のレポートを調べるのが得意。
ねもやん: 勉強会のファシリテーター。組織や人の心理に関心が高い。データだけでは見えない、感情や文化の側面からも考察を行う。
オープニング:みんなも感じていませんか?「時代遅れ」への漠然とした不安
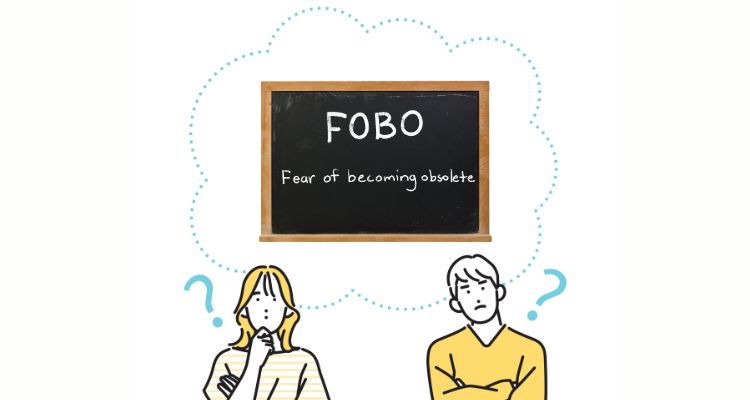

はたけ
お疲れ様です。本日は社内勉強会 〜オシゴトカイワイ〜 に参加いただきありがとうございます。今回のテーマは、私たちとAIの向き合い方についてです。
AIを業務に使い始めてしばらく経ちますけど、うまく使えていますか?私はできる限り活用するようにしていて、効率が相当上がって怖いぐらいです。
そんな中で、ふと「自分のスキルは、このままで大丈夫かな?」「本当にAIに仕事を奪われるんじゃないか…」と不安になったのが、テーマを設定したきっかけです。
調べてみるとこの感情には、名前があるらしいことが分かりました。
“時代遅れになることへの恐れ”「FOBO(Fear of Becoming Obsolete)」って言うらしいですが、みなさんは聞いたことありますか?
今回は、このFOBOについて、はたけさんと一緒に色々と調べてきました。
その正体と、私たちがどう乗り越えていけばいいのかを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。
そもそもこのFOBOって「フォボ」とか「フォーボー」とか言われてますけど最近の言葉なんですかね?

ねもやん

はたけ
2016年のハーバードビジネスレビューに掲載されたマーク・ボンチェク氏の『How to Stop Worrying About Becoming Obsolete at Work ※職場で時代遅れになる不安を解消する方法』が初めてこのテーマに触れたと言われているみたいです。
ただ、ChatGPTやCopilot、Geminiなどの生成AIを個人が使い始めた2023年以降から色々な調査に名称が出てきています。
米ギャラップ社が2023年に行った調査によると、アメリカで働く人の22%が「テクノロジーのせいで自分の仕事が時代遅れになる」と心配しているんです。5人に1人以上ですね。
しかも、2021年には15%だったので、たった2年で7ポイントも上がっている。特に私たちと同世代の18歳から34歳では、不安を感じる人が17%から28%へと、急増しているみたいです。
2022年11月のGPT-3.5のリリースとばっちりタイミングが合います。この記事から2年が経過して、世界的なテック企業がエンジニアをレイオフしたり、「AIによって5年後に無くなる仕事10選!!」 みたいなタイトルの記事や動画が定期的に目に入ってきたり、精神衛生上はあまり良くないかもしれませんね。

ねもやん
FOBOの正体:不安なのは、実は「頑張りたい人」

はたけ
じゃあ、その不安って、どういう人が特に感じやすいんでしょうか?普通に考えたら、変化が苦手な人は不安になりそうな気がします。
そう思いますよね。でも、先ほど紹介した記事を読んだら、現実はむしろ逆みたいです。働く人の約半数が、「現在の職務を高いレベルでこなすスキルを自分は持ち合わせていない」「スキルアップできるなら転職も考える」「会社は従業員のリスキリングに積極的ではない」と答えています。
学びたい気持ちはすごくあるのに、その機会を会社が提供してくれないことに不満を持っているみたいです。
あくまでアメリカの労働者の話ですが、新しい技術にアンテナを張っていて、スキルアップにも意欲的な「感度の高い人」ほど、強くFOBOを感じる傾向にあるそうなんです。

ねもやん

はたけ
面白い!時代の変化に敏感だからこそ、逆に不安になってしまうってことか。
まさに。時代の波を人一倍感じているからこそ、「このままじゃヤバいかも」と思ってしまう。そして、その不安の根本にあるのは、単に仕事を失う恐怖だけじゃなくて、「AI時代に本当に必要なスキルって何?自分はそれを持ってるの?」という、未来が見えないことへの不安が大きいみたいです。

ねもやん
私たちができること:4つのアクションと「主体性」

はたけ
じゃあ、このモヤっとした不安を前向きな力に変えるために、自分達では何ができるんでしょう?ねもやんさん、何かヒントになる情報はありますか?
はい、米フォーブス誌の記事に、具体的な4つのアクションが提案されていました。

ねもやん
① AIを積極的に「知る」
自分の業界でAIがどう使われているかを知れば、自分がどこで価値を出せるかが見えてくる。
②好奇心を持って「学び続ける」
会社の研修を待つのではなく、セミナーやオンライン講座などを活用して学び続ける姿勢が大事。
③「人間ならではのスキル」を伸ばす
複雑な問題解決能力、チームワーク、共感力、創造性など、AIが苦手なことを意識して伸ばす。
④ キャリアを「柔軟に考える」
自分を「スキルの集合体(ポートフォリオ)」として捉え直し、柔軟にキャリアを考える。
この中で、はたけさんは何が気になりますか?

ねもやん

はたけ
AIを積極的に「知る」というのは、上の世代を見てて、なるほどと思うところがありますね。
今の40代後半〜50代以上の管理職の人たちって、多分PCやインターネットを職場で使い始めた最初の世代のはずなんですよね。IT技術の発達と一緒にキャリアを積んだから、効果的な使い方や、逆に使わない方が良いケースもわかっている方が多いように思います。AIをみんなが使い始めた今とシチュエーションが似ているんじゃないかな。
とにかく使い倒して、進化を観測しながら、AIがやった方がよいことと自分でやった方がよいことのそれぞれを知るのが、恐れの克服に繋がりそうに思います。
本当にそうですね。あと、色々な記事で共通して言われていたのが「主体性」ですよね。「会社が何かしてくれるのを待つ」んじゃなくて、「自分の学びは自分でつくる」というスタンス。なんなら会社に「こういう研修をやってください!」と提案するくらいの積極性が、これからは必要なのかもしれません。

ねもやん
社員の不安に会社が寄り添う:カギは「心理的安全性」と「信頼」

とはいえ、社員個人のやる気だけでは限界がありそうです。会社側のサポートもやっぱり欲しいですよね。はたけさん、会社側の課題についてはどんなトピックがありましたか?

ねもやん

はたけ
既存の社員への研修制度は最低限あってほしいですが、それ以上に「会社のカルチャー」、特に「心理的安全性」がFOBOに及ぼす影響は大きそうです。「新しいことに挑戦して失敗しても大丈夫だよ」という空気がないと、せっかく学んだスキルも怖くて使えませんよね。
確かに!失敗を責められたら、何もできなくなってしまいます。うちの部署は比較的大丈夫かな…?

ねもやん

はたけ
AIの導入はコスト削減、効率化、サービス開発など経営視点で語られがちです。今、DXとAIの利活用を書いていない上場企業の経営計画資料はないんじゃないないかと思います。こういうことがトップダウンで進んだ場合、私たち現場の気持ちが置いてけぼりになりがちです。
あるレポートでは、会社は「社員がAIをサボるために使うのでは…」と疑ったり、社員は「AIに評価されて解雇されるのでは…」と不安になる。このお互いの不信感が、一番の壁になっているという指摘もありました。
不信感を減らすためには、会社も社員もAIをどういう目的で使うかを開示しあうことが大事だと思います。例えば会社は「AIを使って会社や事業のこういう課題を解決したい、そしてAIだけを使った人事評価は行わない」と説明できると思いますし、社員側も「こういう成果を出すために、AIで効率化して時間を捻出したい」など互いにデメリットにならない目的・用途を共有するコミュニケーションが必要になるでしょう。
日本で働く私たちへのヒント:「弱み」じゃなく「強み」に注目する

はたけ
このFOBOの問題って、日本だと、またちょっと違う難しさがありそうだなって感じました。日本の働く人って、世界的に見てもストレスが高く、仕事への意欲(エンゲージメント)が低い傾向にあるそうです。その上で、日本の会社って、個人の「弱みや欠点を見つけて、そこを直させようとする」文化が根強くありませんか?
ああ、分かります…。「君はここが足りないから、ちゃんとやりなさい」みたいな。

ねもやん

はたけ
そうそう。その文化がFOBOと結びついてしまうと、「あなたのスキルは足りないからAIに奪われるよ」というネガティブな形でスキルアップを迫ることになり、逆効果を招いてしまいます。どんどん萎縮してしまいますよね。
そこで提案されているのが、発想の転換です。一人ひとりが元々持っている「強み」を見つけて、それを活かしながら新しいスキルを身につけられるように応援する、というポジティブなアプローチへの変化です。これは、上司部下の間だけじゃなく、同僚でも同じことが言えます。

ねもやん

はたけ
逆説的ですけど、AIと上手く付き合っていくためのカギは、「人を大切にする文化」をつくることにあるんですね。「私はあなたのことを信じてるし、成長を本気で応援するよ」というメッセージを伝え続けることが、結果的に組織全体の力になるみたいです。
まとめ:AI時代にこそ価値が高まる「私たちの能力」とは?
今日は「FOBO」をテーマに、その正体から私たちにできること、会社に求められることまで見てきました。変化に敏感で頑張っている人ほど感じやすいこの不安に対して、個人は主体的に学び続け、人間らしさを磨くこと。そして会社は、挑戦できる信頼の置ける場所をつくることが、すごく大事だとよく分かりました。

ねもやん

はたけ
AIをただ怖がるんじゃなくて、私たちも組織も、AIと一緒にアップデートしていくチャンスだと考えるマインドセットが大切ですね。
本当にそうですね。最後に、今日参加してくださった皆さんに、一つ質問を投げかけて終わりたいと思います。AIの進化が私たちの想像以上のスピードで進むのは、もう間違いない。そんな時代だからこそ、「テクノロジーが進化すればするほど、逆に輝く“人間ならではの強み”」って、あなたのお仕事周りだと具体的に何だと思いますか?

ねもやん

はたけ
ぜひ、今日の話をヒントに、皆さん自身の答えを探してみてください。本日はご視聴ありがとうございました!