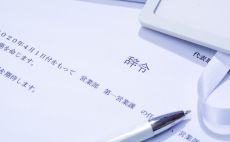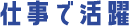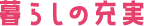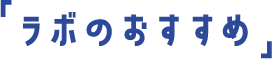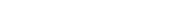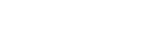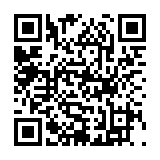転職1年目、なんでも相談室
「子どもが欲しい。でも仕事も大事…」みんなは両立の不安をどう乗り越えてる?
育児をしながら働くって、実際どんな感じだろう?いまは想像しかできない未来。でも、いずれ自分にも起きるかもしれないこととして、知っておきたい!今回はそんな方のために、働くママ・パパ20人の“リアルな毎日”を集めました。「こうすれば完璧」ではなく、「こうすればやっていける」。自分らしい“両立”を見つけるきっかけに、なりますように……。
公開 : 2025/06/26 更新 : 2025/11/25
新しい職場・仕事で活躍するには何が必要?
転職1年目、なんでも相談室
本連載では、転職後のさまざまな壁を乗り越えて、新しい職場で活躍するためのコツをアドバイス! 入社直前の不安な気持ちから、入社後の仕事・人間関係のトラブルまで、転職後1年目に起こりうる「あらゆるお悩み」を取り上げていきます。
子どもが欲しい。でも、今の仕事も大事。両立ってどう考えたらいい?
転職して1年が経ち、ようやく仕事にも慣れてきました。そろそろ子どもが欲しいんです。でも、ふと不安になります。時短制度はあるけれど、実際に使っている人はほとんどいない。上司に話していいのか、それとももう少し先にするべきか…。周囲の目や、チームへの影響も考えてしまいます。子どもを持ちたい気持ちと、今のキャリアを大切にしたい気持ち。どちらも本音だからこそ、答えが出せずにいます。
モヤモヤする前に知っておきたい。先輩ママ・パパのリアルをのぞいてみて!

こんにちは、『転職そのあとLABO』のはたけです。
今回のお悩みは、「子どもが欲しい気持ち」と「今の仕事を大事にしたい気持ち」、その間で揺れているというもの。これは、これからの人生をちゃんと考えている人だからこそ、抱える悩みだと思います。
『転職そのあとLABO』では今回、実際に両立を経験している20代〜40代の働くママ・パパ20人にインタビュー!さまざまな声を集めて見えてきたのは、「完璧じゃなくていい」ということです。バランスをとるのがうまくいかない日もある。だけど、試行錯誤しながら“自分たちらしいやり方”を見つけている。そんな等身大の姿に、思わず頷いてしまう言葉を記事の前半で共有します。
そして、もし「これから子どもを持ちたいけど、会社にどう切り出せばいいのかな?」と迷っていたら……。そんな方も安心できるよう、社労士の資格をもつ人事担当者に、産育休にまつわる相談の仕方を聞いてきました。記事の後半で紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください!
<目次>
■20代~40代の働くママ・パパ20人に聞いた、“リアルな毎日”
(1)どんな「働き方」を選択した?
(2)パートナーとの「家事・育児の分担」はどうしてる?
(3)今後の「キャリア」はどう考えている?
(4)仕事と育児を両立する葛藤、その乗り越え方
(5)パートナーが勤める会社の子育て支援ってどう?
(6)【まとめ】私って結局、仕事と育児を両立できてる?
■「子どもが欲しいかも」と思ったら。会社に確認しておくと安心なこと
20代~40代の働くママ・パパ20人に聞いた、“リアルな毎日”
「両立してる人って、どんなふうに働いてるんだろう?」
「家事や育児の分担って、実際どうしてるの?」
「この先のキャリア、みんなはどう考えてるの?」
自分にとっての両立をまだ模索しているタイミングでは、誰かに話を聞いてみたいですよね。「こうすればうまくいく」と断言できる正解はないかもしれませんが、実際に両立を選んだ人たちの声の中には、ヒントがあります。まずは、両立に向けて「どんな働き方を選んだのか」から見ていきましょう。
(1)どんな「働き方」を選択した?
『転職そのあとLABO』の読者20名にアンケートをとったところ、「時短でのフルリモートワーク」に高い満足度がみられました。印象的だったのは、回答者の約9割が「今の働き方に満足している」と答えていたこと。完璧な環境ではなくても、自分に合ったペースやスタイルを見つけながら、“わたしらしい両立”を実現しているようです。
「働き方」の選択で知っておきたいのは、2025年4月に育児・介護休業法が改正されたこと。3歳未満の子を持つ労働者には、育児のためのテレワーク導入が努力義務になりました。時短勤務が難しい場合の代替として、テレワークに取り組む企業が増えていくと予想できます。国土交通省「テレワーク人口実態調査」(令和5年度)によると、雇用型就業者のうち、これまでテレワークをしたことがある人の割合は、首都圏で38.1%、全国平均で24.8%です。
とはいえ、日本能率協会総合研究所「仕事と育児の両立等に関する実態把握のための調査研究事業」(令和4年度厚生労働省委託事業)によると、育児のための短時間勤務制度を活用したことがある女性・正社員は51.2%、女性・非正社員は24.3%、男性・正社員は7.6%という結果(※)。「時短」の活用もまだまだ進んでいないのが現状です。柔軟な働き方を実現するため、企業側の制度拡大と、労働者側のありたい姿とのバランスが、より一層大切にされる時代といえそうです。
(※)小学校4年生未満の子の育児を行いながら就労し、約10年以内に妊娠・出産・育児のために離職した経験のない労働者を対象としたアンケート調査

女性
9時~17時(休憩1時間、実働7時間)のフルリモート勤務。おかげで子どもの体調不良でも数時間は働ける環境にあり大変助かっている。
子ども一人時代は10時~17時、二人目が生まれてからは10時~16時。参観日やPTAがある日は在宅勤務にしてもらうなど、個別に対応してもらい助かっている。

女性

男性
平日は朝の準備~送りを自分が対応しており、迎え~寝るまでは基本妻に任せている。
また、上司や同僚が働き方に理解があり、助かっているという声も多くありました。時短やリモートワークといった制度面だけでなく、それを気持ちよく使えるかどうかは、職場の雰囲気や上司のスタンスに大きく左右されるもの。働き方を選ぶうえで、上司やチームのサポートは大きな支えになっているようです。

女性
上司が育児に理解があるのでありがたい。子どもの急な熱でも休むのではなく中抜けが可能。
課長や部長も子育てをしていることへ理解があり、その上で働いていることを褒めてくださるので、それだけでこの会社で働いていてよかったと感じる。

女性
(2)パートナーとの「家事・育児の分担」はどうしてる?
共通していたのは、「きっちり分担を決めすぎないほうがうまくいく」という声。ときには家電に頼りながら、「楽をお金で買ってると思えば、全然気にならない」という、肩ひじ張らない考え方が印象的でした。
一方で、「ゆるくする」だけではなく、大事なのが「情報共有」と「話し合い」です。たとえば、カレンダーに家族・子どもそれぞれの予定を登録して共有したり、保護者LINEや学校・習い事のアプリも夫婦で両方登録したり。“一人で抱えない仕組み”をつくっている方が多くいました。やってほしいことがあるときは、口頭やLINEで伝え合い、事前に予定をすり合わせておくことが大切なようです!

女性
家事・育児の分担は得意&効率の良いほうが担当。お互いの担当分野に口出しをしないことが円満のルールだと感じている。
夫がフリーランスで仕事の予定が都度変わるため、家事・育児の分担はしていない。できる方がやるというスタンス。料理・掃除など家の負担が私に偏っているところは不満。

女性

女性
夫は仕事が忙しくほぼワンオペ状態。食洗器や乾燥機など時短できそうな家電を積極的に導入した。多少汚れてても大丈夫だし、毎日手料理じゃなくても子どもは元気!というマインドで完璧・理想を求めてないようにしている。
(3)今後の「キャリア」はどう考えている?
特に女性は、ライフステージによってキャリアの考え方が揺れやすいです。「キャリアのことまで考える余裕がない」と、日々の忙しさの中で“考えることすら難しい”と感じている人も少なくありませんでした。
■暮らし重視派
女性
上の子が来年小学生になるため、さまざまなことに興味が出てきており、あれがやりたいこれもやってみたいなど挑戦したいことが多く、それをかなえてあげたい気持ちがある。ただ、習い事の時間はどこも基本幼稚園時間に設定されているところがほとんどで、今の仕事をしている以上何もさせてあげられない。そのため今まで仕事を優先してきたが【仕事<子どもとの時間】を大切にしたいという思いが強い。
歳を重ねてきて、体力も衰え、仕事も、子どもの人生も、親のことも、と思うと自分の「キャリア」がそれらの項目の一番上には据えられない。こんな自分でも雇ってもらえて仕事をいただけている以上、頂いているお給料に少し上乗せしてお返しできるくらいの仕事でお返しするか、組織にとっていい人材でいたい、なりたい、という気持ちで毎日の仕事をすることで正直精一杯。

女性

男性
現段階では子どもが小さいので子どもたちとの時間を第一に考えているが、子どもが大きくなったらスキルアップのための自己研鑽をしたい。

女性
育児休業を取得したことで改めて仕事が好きだと実感したため、資格継続のための勉強や講座受講を進めている。
もっと出世していきたいなと思っている。その方がより両立しやすくなると思うし。具体的には、平社員より課長、課長より部長のほうが権限が大きいので、自分(とメンバー)がより力を発揮できるように仕組みを変えられる。そこまでいかずとも、例えば急に何かリスケしなきゃいけなくなったとき「ごめんちょっとここスケジュール調整していい!?」って裁量があるのと「課長、申し訳ないのですが今日このあとダメになりまして変更をお願いしたいのですがよろしいでしょうか?」ってお願いするのだと、前者の方がやりやすいと考えている。

女性
回答から見えてきたのは、キャリアについては、「どういう気持ちで向き合うか」が大切だということです。たとえば、「いつでも選択肢を持てるように、今できることを積み重ねたい」「職場以外にもキャリアについて相談できる人を持ち、定期的に話を聞いてもらっている」など、情報収集への意欲や前向きなマインドを保つための工夫が見られました。

女性
今後のキャリアについては悩むことが多い。今は保育園児なので働きやすいが、小学校にあがってからの方が不安。ただ先のことは不確定な要素が多いので、今は「働けるうちは一生懸命働こう!」と考えている。
長男がもうすぐ5歳。今後小学校、中学校(受験???)など、子どももさまざまな選択肢が出てくる中で、自分にどのようなことが求められるのか今から情報収集している。

女性

女性
子どもがいない同年代の方と同じレベル感でキャリア形成するのは、使える時間が違うので無理と割り切っている。そもそも希望していない。ただ、やりたいことをやれている・ステップアップしている、のような実感がないとモヤモヤする性質のため、安定的に働けていればそれでOK、という感覚とも違く、その中間くらいを目指している。
(4)仕事と育児を両立する葛藤、その乗り越え方
多くの人が直面していたのが、時間の足りなさや、心の余裕のなさ。それでもなんとか乗り越えていくために、大事だといわれていたのが「割り切る力」でした。

女性
子どもの時間軸に合わせてあげられず、自分に余裕がなくなり怒ってしまう場面が増えてしまって自己嫌悪に陥ることがある。完璧を求めすぎず、「まあいいか」の気持ちも大事にして子どもとの時間を取るようにしている。
「会社に貢献できているのか」「迷惑をかけていないか」常々不安になる。自分のスキルと周りの方を比較して落ち込むことも多いが、まずは任された仕事をきちんとこなし、自信をもって仕事をすることを目標に頑張っている。

女性

女性
完璧にこなすことは無理に近いので、<頼れるものには頼る、手を抜くところは抜く>というのを意識。今日はちょっと疲れたから簡単にうどんにしようとか、冷凍食品に頼ったり。すべて絶対に手作りにはこだわっていない。
子どもの体調不良や不定期的な通院など、不確定要素のイレギュラーが多く、業務スケジュールも狂いやすいことがあった。前倒しでできることは先にこなし、“あとでやる”を残さないようにしつつも、ある程度のイレギュラーはもう仕方のないこととして、常に覚悟しておくことが大事だと捉えるようにしている。

男性
乗り切るうえで大切にしたいのは、一人で抱え込まないこと。中でも、「子どもに感謝をしている」という声が印象的でした。
子どもは完璧に守ってあげる存在ではなく、「今日はママ、パパも忙しいんだ」「今はちょっとだけ待っててね」と伝えながら、一緒に日々を乗り越えていく。そんな関係性ができてくると、背負っていた両立のプレッシャーや、「ちゃんとしなきゃ」という重荷が、少しずつほどけていくのかもしれません!

女性
近くに親族がおらず夫婦二人だけでは育児や両立に行き詰まることもあったが、パパママ友やご近所家族と協力体制をあちこちに作れたことで乗り越えられている。仕事が長引いた時に保育園迎えを頼んだり頼まれたりするLINEグループ、友人家族と習い事送迎の分担、週末は合同夕食にして夕飯作りや育児の分担、長期休暇中の家族スケジュールを共有して助け合うなど、周囲と育児シェアすることで乗り越えられていると思う。
葛藤という点では、絶対に子どもの協力があって仕事ができていると思うので、子どもにいつも感謝を伝えて、仕事の話もしている。自分のおかあさんは働いているけれどそれはいいことだ、と思ってほしいから、子どももチームの一員で、とても力になってくれているということを伝えるし、子どもも応援してくれるから、乗り越えられているのかもしれない。

女性
(5)パートナーが勤める会社の子育て支援ってどう?
「リモート勤務ができる」「上司が理解のある人」など、制度面や環境面では自分の職場と大きな差はないという声も。一方で、「育児の負担がママに偏りがち」という、モヤモヤを感じている声もありました。
意外にも多かったのは、「パートナーの会社の制度、あんまりよく知らないかも…」という本音です。せっかく制度が整っていても、それを知らなければ使いようがなく、役割分担にも反映されません。まずはお互いの職場の制度を“見える化”し、「どこで助け合えるか」「もっと分担できるところはあるか」を一緒に話し合ってみると、新しい突破口が見えてくるのではないでしょうか!

女性
夫の会社(上司)も子育てに理解があるので、リモートワークができたり仕事の時間を調整できたりと、柔軟に働ける環境で助かっている。
妻は基本リモート勤務で、月に1〜2回程度の出社のみという働き方。妻の上司も子どもがおり、子どもの体調不良時などにも理解がある良い環境だと感じている。ただ、子どもが二人おり、体調不良が家族内で連鎖することも多く、結果として妻の欠勤が増える傾向があり、評価や業務への影響も気になる。

男性

女性
子どもの急な体調不良が続いた際に、リモートを少し取り入れていただけたのはありがたかったが、その瞬間のみだった。夫の部署は、サポート体制があまりない、または活用しづらい部署なんだなと感じている。
夫は単身赴任中で、2か月に1度しか帰ってこられない。子どもの成長も見れないし、育児参加も難しいため、サポートは0に等しい。

女性

女性
補助金や育休の制度はなく、職業柄時短勤務もおそらく出来ないため、主人が仕事の日は土日含めワンオペ状態。正直まだまだ昔の風潮が残っている会社なので不安だ。
(6)【まとめ】私って結局、仕事と育児を両立できてる?
結果としては、約7割の方が「できていると思う」と回答しました。ただ、それは“どちらも完璧にこなしている”という意味ではありません。
両立は、“理想の形”にぴったりはまることではなくて、日々をやりくりしながら、自分たちなりに回していくこと。「いまの自分、頑張ってるよね」——そう思えたら、それはもう立派な両立です!

女性
リモート勤務のおかげでなんとかできていると思う。また「仕事」と「育児」、まったく違う2つの時間があることで刺激になりリフレッシュできている面もある。プライベートに関しては「完璧」は目指さず、とにかく自分を甘やかして生きている。
両立できている。大きな声では言えないが、自分にとっての一番は子どもで、その比重が高く(両立、といっても比重は半々ではない)、子どもが健やかに成長してくれていて、仕事も続けられている今は、両立できていると考えている。

女性

男性
子どもの性格にもよると思うが、両立はできると思う。その上で、パートナーと協力しながら育児をすることは大切だと感じる。
できていると思う。パートナーとお互い思いやりをもって行動しているので、大小様々なトラブルはあるものの、両立はできている。

男性

女性
仕事で成果を出せているかというと、現時点では納得いく結果は出ていないので、そういった意味では、完璧に両立できているとは言い難い。ただ、「いっぱいいっぱいにならず、心穏やかに過ごせている」という点では、育児と仕事のバランスよく過ごせている、とも感じる。
仕事60%、育児60%くらいの感覚で、計120%をなんとか日々回しているので、両立できているとは思っていない。(100%を超える20%をどうしているかというと、夫と、家事代行と、諦めでなんとか回している状況)。世の中の総合職ワーママはみんなこれくらいの感覚なのでは?と思っている。若い人たちが描くイメージの「両立像」なんて絶対に無理なので、子どもを産んだらいち早く手放すべき。あと、しっかり仕事したいなら夫選びは本当に重要よ。ということを若い女性たちに伝えたい。笑

女性
20人のリアルな声に触れてみて、いかがでしたか?
毎日が手探りで、うまくいかないことだってたくさんある。それでも、自分なりのペースで前に進んでいる。先輩ママ・パパたちの姿から、“両立ってこうでいいんだ”と思えるきっかけがありましたでしょうか?ほんのわずかでも、心が軽くなるきっかけになっていましたら幸いです。
「子どもが欲しいかも」と思ったら。会社に確認しておくと安心なこと

ここからは後半パート!子どもがほしいと考えたとき、会社の誰に相談するといいのでしょうか。今回は、社会保険労務士(社労士)の国家資格を持つ弊社人事の田中さんに、相談する相手や聞き方についてのアドバイスをもらいました。
相談内容によって聞く相手を使い分けよう
産育休の制度に関すること、お休み中のお金のこと、復職したあとの時短勤務制度のことなど、制度面については「人事(労務担当)」に聞きましょう!制度面について一番正確な情報を把握しているのは、人事労務だからです。
また、妊娠したあとに在宅勤務の配慮はしてもらえそうか…など、日々の業務に関わることは「直属の上司」に確認すると良いです。本人の仕事内容によって配慮事項も変わるため、実際に産育休を取得するとなると、上司からサポートを受けられる状態にしておくのが望ましいでしょう。
リアルな体験談を知るには、「実際の産休取得者」に聞いてみるのも一つの手。同じ会社の先輩ママ・パパだからこそ分かる、生きた情報があるとより安心かと思います。
相談相手への聞き方や手段は特段問いませんが、強いて言うなら「直属の上司に話してから人事に相談」という順番は意識したほうが良いかもしれません。上司目線からすると「自分を飛び越えて直接人事に相談された」場合、人によってはあまり良い気持ちがしないからです。また、上司は常にそのメンバー個人のキャリアのことと組織全体のことを考えているため、なるべくタイムリーに相談すると喜ばれる傾向にあります。妊活・育休を考えているタイミング、妊娠したタイミングなどで、都度共有するようにしましょう!
会社に●●の制度があるか確認してみて!
仕事と育児を両立するために、「短時間勤務制度の使い勝手」と「テレワーク/在宅勤務制度の有無・使い勝手」を確認することはマストです。それぞれの制度で確認すべきことは、(1)子どもが何歳になるまで使えるのか、(2)実働何時間から利用できるのか、(3)制度から除外される方はいるのか。短時間勤務制度は法律で義務化されていますが、ルールは会社によって異なるため、できる限り詳細まで確認してください!
まとめ
仕事と育児の両立について、働くママ・パパのリアルな声と、実際に子どもを持ちたいと考えたときの会社との向き合い方をまとめてきましたが、いかがでしたか?
正解や完璧はありません。「これが、今の私にとってちょうどいいかも」と思える形を、家族や周囲と協力しながら探していくことが、仕事と育児の両立においては大切な考え方です。
そしてもうひとつ。両立を支える制度や環境がある一方で、それを直接は使わない同僚たちの存在も、心の片隅に置いておきたいところ。お互いの立場や状況を想像し合うことが、チームとしてのやさしさや働きやすさにもつながっていくはずです。
自分が助けてもらったときには、いつか別の誰かを支える側になれるように。そんな温かい気持ちをもっていれば、この先で仕事と育児の両立に悩むことがあっても、きっと前向きに、少しずつ進んでいけるはずです。

はたけ
『type』『女の転職type』の求人広告制作を担当。エンジニア、営業、接客販売、事務、ものづくり系など、約5年間で200社以上の中途採用に携わる。人事をはじめ代表や社員といった幅広い方々に取材をおこない記事を制作してきた経験から転職そのあとLABOチームにジョイン。好きな食べ物はだし巻き卵。ほっと一息つくような情報をお届けしたい。
田中さん
【保有資格】社会保険労務士、第二種衛生管理者前職ではHRBPのアウトソーシング会社で事務や法人営業の業務を経験。その後type転職エージェントを運営する株式会社キャリアデザインセンターへ中途入社をし、人事部人事課課長として、全社の給与計算や産休育休などの各種社会保険手続き、人事制度設計や運用に携わる。経営の屋台骨となる人事制度の立案などに携われることにやりがいを感じている。